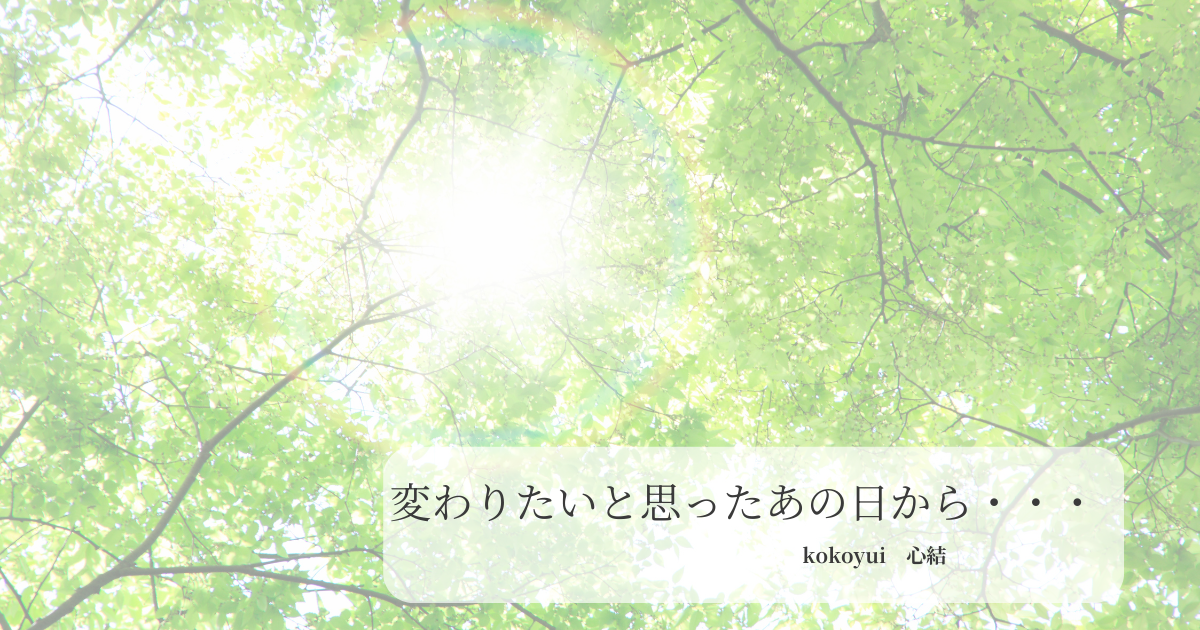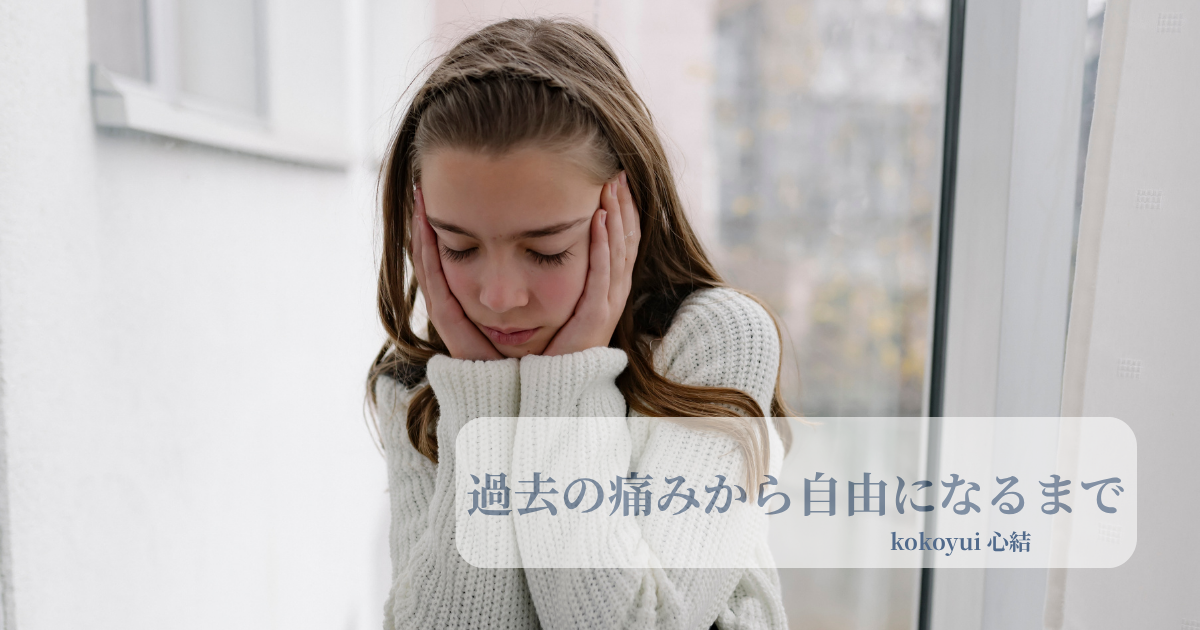赤ちゃんの生活リズムが整わない?シッター体験から学んだ安心のヒント

「朝起きる時間が毎日違う」
「昼寝が長すぎたり短すぎたり、リズムがバラバラ」
「夜にまとまって寝てくれない」
赤ちゃんの生活リズムに悩むママはとても多いです。
育児書やネットには「早寝早起きを習慣に」「授乳やお昼寝の時間を決めましょう」と書かれていますが、実際には思うようにいかない日もたくさんあります。
私はベビーシッターとして現場で赤ちゃんと関わる中で、
「生活リズムが整わないことは自然なこと」だと実感しています。
今回は、実際の体験談と専門的な視点から、ママが少し安心できるヒントをお届けします。
シッターで出会った赤ちゃんのエピソード
あるご家庭でお世話になっていた生後8か月の赤ちゃん。
ママは「毎日同じ時間にお昼寝させたいのに、全然うまくいかないんです」と悩まれていました。
確かに、ある日は午前中にぐっすり眠るのに、別の日は全然寝ない。
午後も30分しか寝なかったり、逆に2時間以上寝てしまったり。
でも、数回関わっていくうちに私は気づきました。
「その日の遊び方や体調、朝の起きる時間によってリズムは変わるけれど、ちゃんと“眠たいサイン”は出しているんだ」
たとえば、
- 目をこすり始める
- 頭をかきはじめる
- 急に泣き出す
- 抱っこを求める
赤ちゃんは言葉を話せない代わりに、体としぐさで「眠いよ」「休みたいよ」と伝えてくれているのです。
生活リズムの発達
赤ちゃんの生活リズムは、生まれてすぐに整うわけではありません。
- 新生児期(0〜2か月):昼夜の区別がなく、2〜3時間ごとに授乳と睡眠を繰り返す
- 生後3〜5か月:少しずつ昼と夜の区別がつき始める
- 生後6〜8か月:昼寝は2〜3回。夜はまとまって眠れるようになりやすい
- 生後9か月以降:日中は午前・午後の2回昼寝が多くなる
つまり、生活リズムは“自然に発達していくもの”。
大人が完璧に整えようとしなくても、月齢が進むにつれて少しずつ安定していきます。
ママに伝えたい安心のポイント
① 「整わないのは普通」と知る
「うちの子だけダメなんだ」と思わなくて大丈夫。
赤ちゃんの生活リズムは、個性と成長のペースによって大きく違います。
② 無理に時間で区切らない
「何時になったから寝かせる」よりも「赤ちゃんの眠たいサインを見逃さない」ことの方が大切です。
③ ママ自身のリズムも大事に
赤ちゃんのリズムを優先するあまり、ママが疲れてしまっては意味がありません。
できる範囲で「今日は昼寝が短いから夜は早めに休もう」など、柔軟に考えてOKです。
一人で頑張っているママへ
「毎日リズムを整えなきゃ」と頑張りすぎて、つい自分を責めてしまうことはありませんか?
でも、生活リズムが乱れるのは赤ちゃんにとって自然なこと。ママのせいではありません。
むしろ、毎日一生懸命に赤ちゃんを見守っているからこそ「整わない」と感じてしまうのだと思います。
一人で頑張りすぎなくても大丈夫です。
「今日はこうだったな」と振り返るだけでも、十分に愛情を伝えています
ママへのメッセージ
赤ちゃんの生活リズムは、一日ごとに違って当たり前。
それでも「どうしてうまくいかないんだろう」と悩むのは、ママが一生懸命に向き合っている証です。
🌸心結LINEでは、一人で頑張りすぎてしまうママの心が少しでも楽になるようなお話や、安心して子育てできるヒントをお届けしています。
「私だけが頑張ってるんじゃない」と感じられる場所として、ぜひ気軽につながってくださいね。
👉 [LINE登録はこちら]